九十九
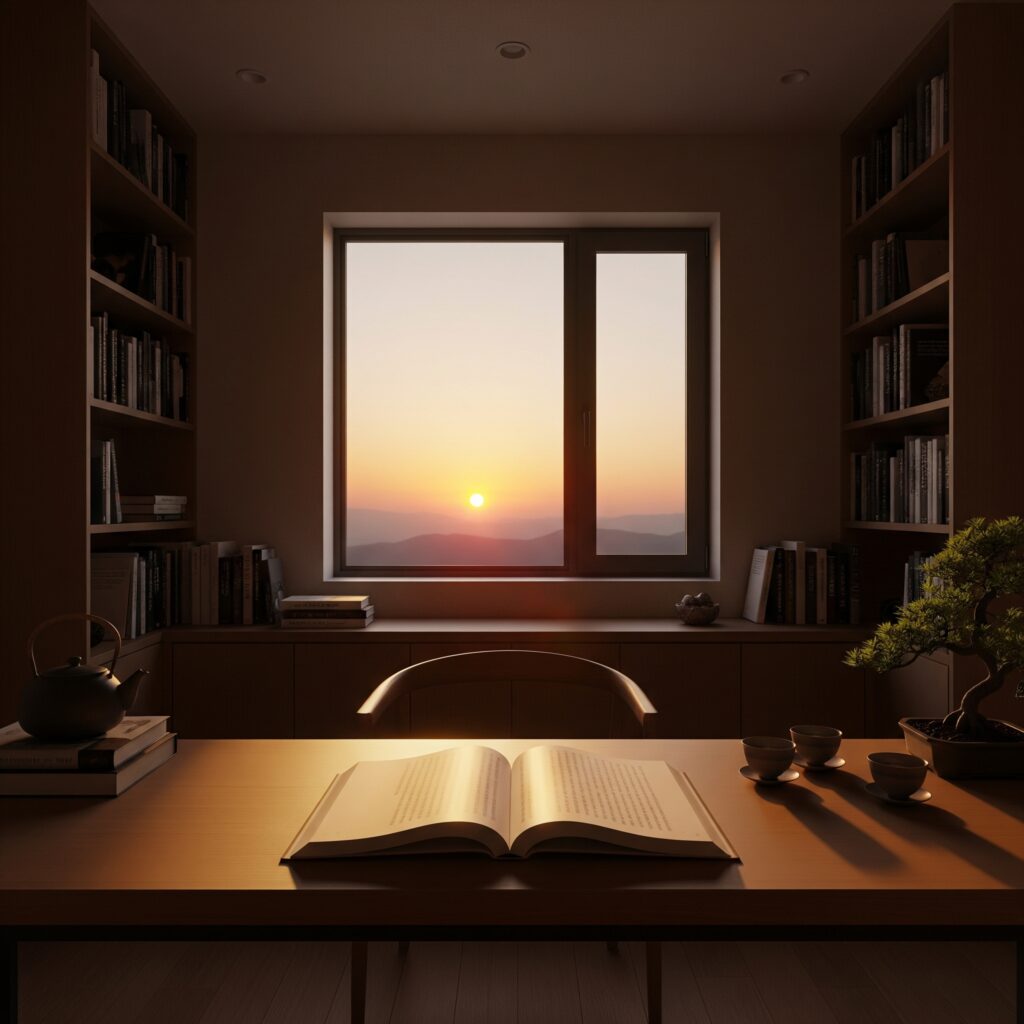
年齢が少し高くなってくると、これまで関心がなかった事柄が身近なものになってくる。とくに身近な人が亡くなった場合などは、死や老いというものが、否が応でも他人事ではなくなる。
私の書棚を眺めてみると、昔だったら絶対に読むことが無かった本が数冊並んでいる。どれも死や老いに関するもので、ある意味で変化球的な本である。私の嗜好性を反映しているともいえる。人生のくくり方、私の死亡記事、往生際の達人、死をどう生きたか、辞世のことば、弔辞、追悼の達人、江戸人の生と死、等々。執筆者は、社会学者、医者、作家、随筆家などさまざまで、興味深い。
昨年のことになるが、百人一首の解説書を読んでいたら、次の和歌が紹介されていた。伊勢物語に掲載されているそうである。少しばかり、老いと関係がある。
百年に一年足らぬ九十九髪
我を恋ふらし面影に見ゆ
和歌の意味は、百歳に一年足らない九十九歳の白髪の老婆が、わたくしを恋しているらしい、まぼろしに見えるようだ、とでも理解すればよいのだろうか。この老婆は、小野小町のことで、小町伝説は全国各地に残っている。
私の関心は、「九十九」をどのように読んだらよいか、というものである。百から百の横棒を引き算すると漢字の「白」になるから、九十九歳を白寿と呼ぶことは良く知られている。「九十九」は少し見慣れないが、「つくも」と読む。広辞苑にも掲載されている。よって、上述の和歌を通しで詠むと、以下のようになる。
ももとせにひととせ足らぬつくも髪
我を恋ふらし面影に見ゆ
「ももとせ」とか、「つくも」とか、普段あまり使わない言葉が口から出てくると心地よく、三日坊主でもよいから、少しは和歌を勉強したくなる。
もう一つ記憶にあるのは、明治の文豪森鷗外の遺言「・・・余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」である。鷗外は、軍医として、そして作家として、公人と私人の二刀流を極めた。人生の最後は、生誕の地である石見(現在の島根県)と自らの本名である森林太郎によって、「野に生きる」意思を示したのではなかっただろうか。墓表は、「森林太郎墓」とのみ中村不折の書で書かれている。
自分自身で、自分のことを対象にして、人生のくくり方、私の死亡記事、往生際の達人、死をどう生きたか、辞世のことば、弔辞、等々を短文でよいので、つくってみたらどうなるか。それらをまとめて整理すれば、自伝の類になる。人生史(ライフヒストリー)である。「私は誰」の思考実験としても面白い。
(金安岩男 慶應義塾大学名誉教授)
